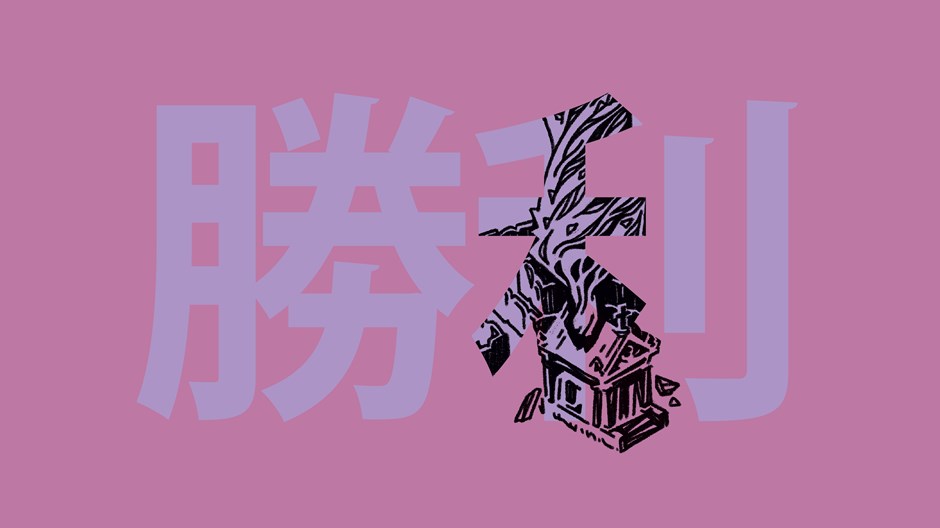
この熟読シリーズでは、聖書学者が自身の弟子訓練の土台となり、今日まで影響を与え続けているみことばの中で、自身の専門分野である個所について思い巡らします。
ラテン語のフレーズで、聖公会祈祷書に含まれているものがある。「Media vita in morte sumus」生のただ中にあって、私たちは死の中にある、という意味だ。
歳を重ねるにつれ、私の人生における想定外の新たな現実の一つは、「残念ですが」という前置きで始まる、いわゆる「悪い知らせ」を告げる電話やメールの量が増えてきたことだ。そして、年老いるにつれ、空白だった予定表が葬儀で埋められることが増えてきた。これは驚くにはあたらない。誰も皆、年を取る。そして老いれば必ず、一つの例外もなく、死に至る。私たちは死の中にあるのだ。
私はこの現実から意識的に逃げてきた。あるいは考えたり、読んだり話したり、執筆、家族の世話などで自分を忙しくさせることによって、無意識のうちに逃げてきたのかもしれない。もしかしたら、活動し続けるために、自分に言い聞かせる嘘の一例として、死は私に関係ないと言い聞かせて、世界でいちばん楽観的な人間を演じてきたのかもしれない。少なくとも、死が自分に関係ないかのように生きてきた。
もちろん、死は私のごく近い人々の間に存在しなかったわけではない。たとえ一瞬にしろ、あの恐ろしいものの匂いを嗅いだことはある。その匂いは非常に特異で、けっして忘れることができない。十代の時、親しい女友だちが父親の散弾銃で自殺し、きょうだいに発見された。彼女の葬儀の際、カリブの島に容赦なく照りつける太陽の下、私は生まれて初めて死の匂いを嗅ぎ、それを感じた。死の邪悪性と力とが私を立ち止まらせた。
その数年後、私がいちばん仲良くしていた、きょうだいと言っていいいとこが、モルヒネを過剰摂取し、やはり彼のきょうだいに発見された。あの匂いがまた、電話を通してでさえ漂ってきた。しかし、最も強く感じられたのは葬儀の時だ。死の匂い、その力、それを前にしての私たちの無力。それ以来、私の祖父母は皆、亡くなり、死の匂いは何度も私のそばを通り過ぎていった。
しかし今、中年を過ぎて、他人ではなく自分の体の検査結果を待つ間、一瞬恐れを感じる時、主がまもなく再臨されるのでない限り、私はやがて死ぬのだと実感するようになった。特にコリント第1の15章は私に教えてくれた。人生が全盛期にある、つまりmedia vita(生のただ中にある)時でも、死は私にやって来るというのが現実なのだ。
使徒パウロは、私より死をよほど身近に(しかも迅速に来るものとして)知っていた。そもそも彼の生きていた世界には、抗生物質もワクチンも現代医学もなかったのだ。単純な感染症が命取りになる可能性があった。
使徒として、パウロは自身の苦難について複数のリストを記した。古代哲学者はこれを苦難のカタログと呼んだ。その一つがコリント第2に記されている。
私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちは、いつもイエスの死を身に帯びています。それはまた、イエスのいのちが私たちの身に現れるためです。私たち生きている者は、イエスのために絶えず死に渡されています。それはまた、イエスのいのちが私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして、死は私たちのうちに働き、いのちはあなたがたのうちに働いているのです。(4:8–12)
パウロはこの他にも、その働きの中で死の危険を味わったことが何度もあった(2コリント11:23–30)。エルサレムでは、危険な暴徒に殺されかけた(使徒21:27–36)。その後、ローマに裁判を受けに行く道すがら、賢明とは言えない旅の途上、地中海でおぼれかけた(使徒27)。
しかも、パウロは使徒であっただけでなく、牧師でもあった。つまり、死にゆく人々のかたわらに座して祈ることが、たびたびあったであろう(ピリピ2:25–27)。主にある多くの兄弟姉妹の葬儀に関わったであろう。使徒20:9–10によれば、パウロは自身の説教が長く続いたために、眠り込んでしまった青年の息を吹き返させた。この青年は窓から落ちて、その衝撃で死んだと思われる。パウロは古代の預言者のように青年の身体の上に自分の身をかがめ、青年を生き返らせた。
自分の死に関するパウロの見解はピリピ書に見られ、そこで彼は次のような究極の考えを記している。「私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか、私には分かりません。」(1:21–22)
パウロは他の人たちの死や、自身が命を落としそうになった体験をとおして、死の臭いを嗅いでいた。だが、様々な死の中でパウロの思いをいちばん強くとらえていたのは、イエスの死だったと言ってよいだろう。パウロの頭の中にはいつもキリストの死があった。
パウロ書簡を読むと、聖霊の助けによって、キリストの十字架の死の意味を理解しようとしていた一人の人間が浮かび上がる。イエスが本当にメシアだったのなら、なぜ死なねばならなかったのか。しかも、なぜよりによって十字架上で死なねばならなかったのか。この不名誉な死は、イエスのアイデンティティについて何を語るのだろうか。彼の死は、イエスと神との関係について私たちに何を告げるのだろうか。彼の死は家スラエル民族、この世界、そしてパウロ自身とどう関係するのだろうか。
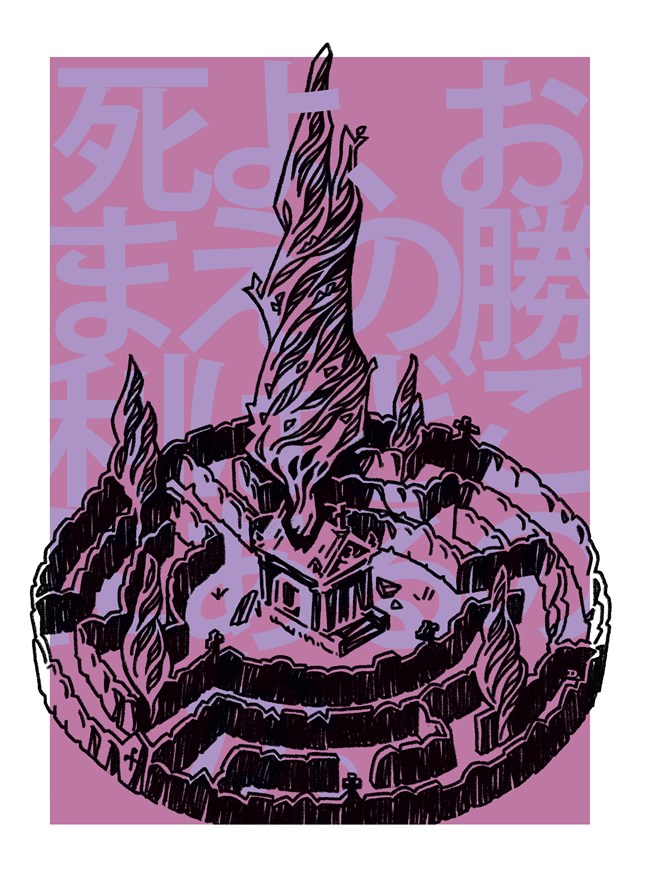
パウロは十字架についての神学者だった。つねにキリストの十字架の死を告げ知らせていた。ローマ帝国社会では、このような告知は馬鹿げたものだった。だがパウロと初代クリスチャンたちにとっては、良い知らせだった。なぜか。それは、イエスの十字架に続いて、栄光に輝く復活が起きたからであり、そこで死が決定的に打ち負かされたからだ。
新約聖書は、イエスの復活についての記述に満ちている。その教えはたとえ話に埋め込まれていることもあれば、終末的イメージによって象徴的に表現されていることもある。しかし、イエスの復活についての最も詳細で分析的な解説は、コリント第1の15章に見られる。
約1年半コリントに滞在し、複数の教会を開拓し、建て上げた後、パウロは別の場所で宣教の働きを続けるために旅立った。パウロが去ったことで、かつて活力に満ちていた教会がいちじるしく弱体化したことは明らかだ。彼が去ってまもなく、コリントの諸教会は、パウロが教えたのとはかけ離れた世界観に染まってしまった。実際、その行動は不信者とさして変わらなかった。分断、うぬぼれ、罪ある性的行動、自己中心、霊的な賜物の乱用がまん延していた。これらすべてが示していたのは、コリント人には、キリストにある信者の最重要点、すなわち十字架上で表された愛が欠けていたということだ。
コリント人に手紙を書く中で、パウロは基本、つまり福音そのものに立ち返る必要があった。そこで、彼は15章の冒頭で、コリント教会に福音の内容と、福音が信頼に足るものであることを思い起こさせた。「私がどのようなことばで福音を伝えたか、あなたがたがしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなたがたが信じたことは無駄になってしまいます。」(2節)と彼は述べる。
そして、福音の内容を説明する。「キリストは、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおりに、三日目によみがえられたこと」(3–4節)。コリントの信徒は、以前に救いの言葉として受け入れたはずのこの福音について、問題ある考え方をするようになっていた。1–4章において、パウロはイエスの十字架について彼らの考えを正す。そして15章において、イエスの復活について彼らの見解を正したのだ。
復活についての彼らの問題点は二つあったようだ。第1に、復活などあり得ないと主張する人々がいた(15:12–19)。パウロはこの主張に反論し、キリストご自身が死者の中からよみがえったことを思い出させる。これは聖書が約束したことであり、(パウロを含む)使徒たちおよび他の多くの人々が実際に証言したことである。キリストが死者の中からよみがえったのだから、復活などないという主張は全くの偽りである。
ここで根本的に重要なのは、パウロがどのように復活の事実を主張したかに注目することだ。具体的には、パウロは抽象的な議論を用いなかったことに注目すべきである。一部の宗教哲学者のように、復活は現実の本性の一部であって、死後には必ず新生があるといった主張をパウロはしなかった。
確かにパウロも、復活の仕組みを説明するために自然界を参考に持ち出している。しかし、それは彼の主張の根幹ではない。むしろ、自然についてのパウロの適用の仕方は、カール・バルトの言葉を借りれば「真理についての世俗的たとえ」として見るべきである。
パウロは、たとえて言えば四季を観察することによって復活を証明しようとはしなかった。冬が死に絶えると、やがて必ず春の命が巡ってくるからといって、この死から命への移行が現実の本質に組み込まれているわけではなく、したがって復活が存在することを証明するのでもない。この場合において、イエスの復活は、より大きな現実のほんの一部にすぎなくなる。
そうではなく、パウロの主張は具体例から一般化するものだった。復活は存在する。なぜなら、イエスが死者の中からよみがえったからだ。その逆ではない。パウロにとって、現実はキリスト中心だった。信者にとって、苦難の後には必ず喜びがあり、金曜日の後には必ず日曜日が来る。なぜなら、イエスの場合にそうだったからだ。
復活についてのコリント人の第2の問題点は、復活がどのように起きたかにあったようだ。この弱い肉体が朽ち果てた後、栄光ある朽ちない身体を受け取ることが、どうして可能なのか。死なない者として復活する、しかもぼんやりした霊的な意味ではなく、肉体をとって復活するのが、どうやって可能なのか。これは実にむずかしい(回答不能とも言える!)質問であり、パウロはそのような質問への回答として答えたのではなかった。
先に言っておくが、私とて、仕組みを理解できない事柄について信じるのはむずかしい。しかし、だからといって、その事柄が不可能だということにはならない。巨大な航空機が離着陸し、空を飛んでいく仕組みを私は理解していない。だが、それは実際に起きている!
コリント人がその不信仰を克服するのを助けるために、パウロは一つのたとえを語る。種が地面にまかれる時、ただの種に見える。やがて腐敗を経ると、異なるかたちで姿を現す。それは異なる体だ。同じように、人の肉体は朽ちて腐敗した後、神の力によって新たな物質によみがえる。それは、私たちの理解を超えた性質を持つ栄光の体である。
ここでコリント第1の15章を要約するとしたら、この問いで言い表せるかもしれない。「あなたは神の力を信じるか?」パウロは神の力を信じていた。その神は死者をよみがえらせるお方だ。だから、パウロは勝ち誇った口調でこの章を締めくくる。
「この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが、死なないものを必ず着ることになるからです。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記されたみことばが実現します。
『死は勝利に呑み込まれた。』
『死よ、おまえの勝利はどこにあるのか。
死よ、おまえのとげはどこにあるのか。』
死のとげは罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。」(53–57節)
このことは理解不能だが、パウロは信じていた。彼が信じていたわけは、神の力を信じていたからだ。その力はイエスの復活において表された。アウグスティヌスはこのみことばについて、次のように述べている。「無からすべてのものを造られた神が、人の肉体から天国の体を造られることに、人々は驚嘆する。(中略)あなたが存在しなかった時にあなたを造ることができたお方が、かつてのあなたの体からあなたを造り直すことができないとでもいうのだろうか。」
死は現実的だ。私たちの体は壊れ、朽ちていく。どんなに抵抗しても、この世の生というハイウェイは、生から死という一方通行だ。そして時には、肉体的全盛期のまっただ中においてさえ、死は姿を現す。事故や予期せぬ病気や、暴力的に命を奪われることもある。生のただ中にあって、私たちは死の中にある。
私の願いは、日々弱っていくこの体が、イエスの体のような体をまとって死なないものによみがえることだ。イエスは初穂として私に先立っていかれた。私は彼についていく。なぜなら復活という贈り物において表されたイエスの愛は、死にさえ打ち勝つからだ。
私たちはこのような知識を持って生きることができる。すなわち、イエス・キリストの復活に含まれている、死そのものよりも大きな現実があるという知識だ。信仰によって彼と結び合わされた私たちは、たとえ疑いや苦難にさいなまれる時でも、知っている。この朽ちるものは朽ちないものを着るようになるのだ。
Osvaldo Padillaはサンフォード大学ビーソン神学部神学教授である。

Annual & Monthly subscriptions available.
- Print & Digital Issues of CT magazine
- Complete access to every article on ChristianityToday.com
- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives
- Member-only special issues
- Learn more
Read These Next
- Trending
 While we pray for peace, we need moral clarity about this war.
While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine
 A Christian reconciliation group in Israel and Palestine warned that war would come. Now the war threatens their relevance.españolالعربيةFrançaisрусскийУкраїнська
A Christian reconciliation group in Israel and Palestine warned that war would come. Now the war threatens their relevance.españolالعربيةFrançaisрусскийУкраїнська - Editor's Pick
 How groups like Hillsong learned to let go of the literal in favor of creative collaboration.españolPortuguês
How groups like Hillsong learned to let go of the literal in favor of creative collaboration.españolPortuguês













